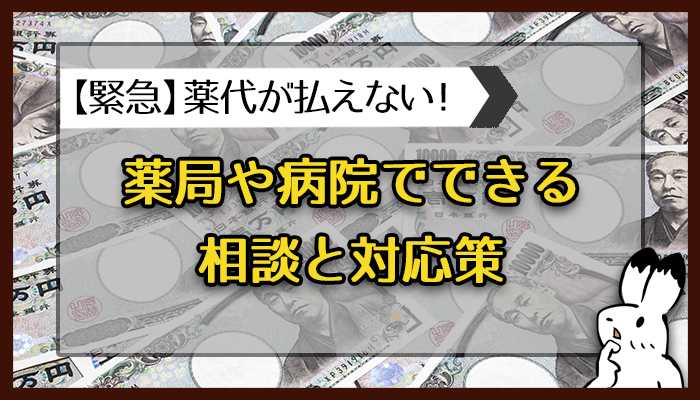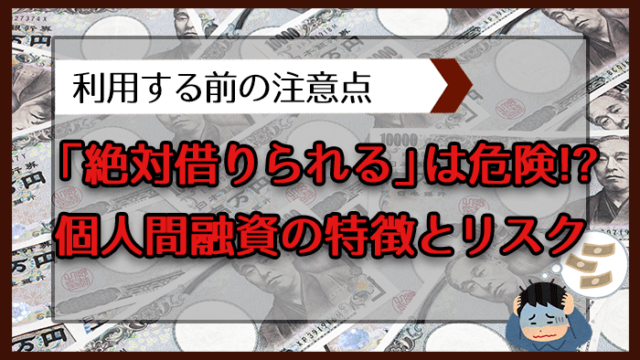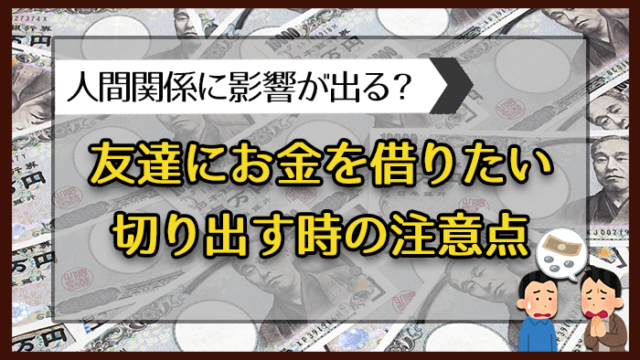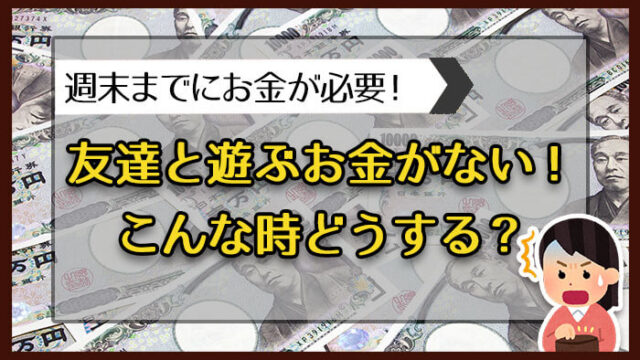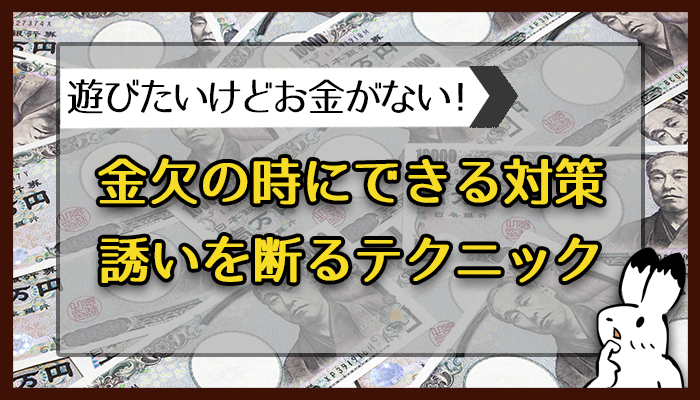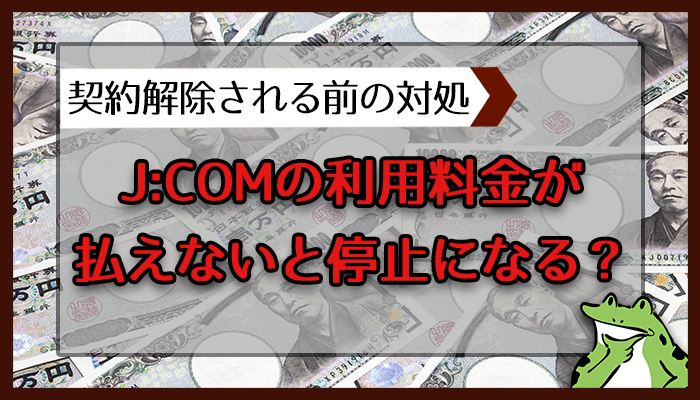「病院の薬代が高くて払えない…」という人はいませんか?
病院からもらう薬は保険が適用されるものが多いため、1回あたりの負担はそれほど大きくありませんが、持病の治療などで継続的に処方を受けるとなると、かなりの出費になることもあります。
薬代が払えない時の対処法
特に新しい薬や一部の生活習慣病の薬などは、保険を使っても高いことも多いものです。
かといって治療を受けないわけにもいきませんし、市販薬で済ませようとすると、むしろそっちのほうが高額だったなんてこともザラにあります。
そんな薬代で悩んでいる方のために、このページでは利用できる公的な制度や、おすすめの金策方法などについてまとめました。
「万が一、薬代をずっと払わなかったらどうなるのか?」についても解説していますので、ぜひ参考にしてみてくださいね。
薬代が払えないときの解決策・制度まとめ
薬代が払えないと言っても、人によって状況はさまざまです。
薬局窓口で薬代が払えない場合は、以下のような方法が考えられます。
- 別の日に支払うまで待ってもらう
- クレジットカードを使う
- お金を用意してから調剤薬局に行く
もしくは、通院する前に薬代が払えないとわかっている場合には、以下のような方法があります。
- 医師に薬の内容や量を調整してもらう
- 院内処方で対応してもらう
- ジェネリック医薬品で処方してもらう
また、たび重なる通院で医療費負担が増えている人が利用できる制度には、以下のようなものがあります。
- 高額療養費制度
- 高額医療費貸付制度
- 無料低額診療制度
- 傷病手当金
- 医療費控除
それぞれについて、くわしく解説していきます。
薬局で薬代が払えない場合の対処法3選

病院で処方箋を受け取ったけれど、その場でお金が足りなくて薬代が払えない場合の対処法はいくつかあります。
中には、診察費が思った以上に高すぎて薬代がなくなってしまった人もいるかもしれませんね。
そのまま処方箋を出さずにいると、確かに薬代は払わずに済みますが、病状が悪化する危険性がありますし、病院で払った「処方箋料」もムダになってしまいます。
健康のためにも、なんとか支払うための方法を考えていきましょう。
ここでは、3つの方法をご紹介していきます。
支払いを待ってもらう
薬局で予想外の金額を提示されたら、まずは「お金がない」ということを伝えてください。
何度も支払いができていない場合でなければ、別日の支払いにしてもらえる可能性があります。
周囲の目が気になるかもしれませんが、財布にお金が入っていない以上、払いたくても払えません。
それに身体の具合が悪い以上、薬を我慢するわけにはいきませんよね。
ただし、できれば処方箋を出す前に、薬の値段がどれくらいになるのか確認しておきましょう。
後日改めて薬局に行く
まずは薬局窓口でいくらぐらいになるのかを確認し、緊急性の高い薬でなければ、お金を準備してから薬を受け取ることを検討してみましょう。
処方薬は病院の近くの調剤薬局に限らず、全国どこでも受け取ることができます。
ただし注意したいのは、処方箋には有効期限があることです。
処方箋の有効期限は「発行日を含めて4日間」と意外と短い上、土日祝日も含まれますので、短期間でお金を用意する必要があります。
後払い出来る決済方法を使う
調剤薬局というと「現金のみの取り扱い」というイメージが強いかもしれませんが、最近は時代の流れに合わせて、クレジットカードや電子マネーが使えるところも増えています。
処方箋はどこの薬局で出してもOKなので、あらかじめキャッシュレス決済ができる薬局を探して行くのがおすすめです。
また、ウエルシアやスギ薬局、セイムスなどのドラッグストアでも処方箋を扱っているところはたくさんあります。
そうした薬局ならクレジットカード決済に対応している可能性が高いでしょう。
定期薬が高くて払えない場合の対処法3選
継続的に服用している薬の場合、病院にかかる前からすでに薬代が払えないことがわかっている場合もあるかと思います。
そんな時は、あらかじめできる対策をしておきましょう。
たとえば、処方箋を書く医師に、なるべく薬代が安く済むよう前もって相談することが可能です。
また、処方箋の書き方によって安いジェネリック医薬品を使えるかどうかが変わるため、そのあたりも含めて相談できます。
健康保険が適用される治療薬と適用されない治療薬どちらにも共通する方法ですので、ぜひ参考にしてみてください。
薬の量・種類を調節してもらう

「もう財布にお金が入っていない、どう考えても払えない……」
事前にそういった状況が分かっている場合は、お医者さんに相談してみてください。
自分の症状を的確に伝えたうえで、合わせて「お金がない」ということをきちんと伝えましょう。
勇気が必要になる申し出ですので、なかなか声に出して言いにくいかもしれません。
病気や怪我が重篤であれば、そんなことも言っていられない状態になることもあります。
ただ普段から意思疎通ができていれば、お医者さんのほうから「払えそうですか?」と気遣ってくれるほどの関係性を築くこともできます。
どうしても言いにくい場合は、紙やスマホに状況について書いて、それを見せるようにするとスムーズです。
処方するタイミングや量、種類を調節してもらえそうであれば、積極的に頼っていきましょう。
ジェネリック医薬品で処方してもらう
前項に対応する項目ですが、できれば「ジェネリック医薬品」を使えないか提案してみてください。
ジェネリック医薬品とは、成分・効能が同様の後発医薬品です。
先に出た新薬の特許が切れたあとで開発されるため、研究費用がかかっていません。
そのため安価で購入できますが、成分は同じなので安心して利用できます。
調剤薬局などで「ジェネリック医薬品が利用できますが……」と訊ねられたら、積極的に利用していきましょう。
院内処方で対応してもらう

あまり知られていませんが、「院内処方」にしてもらうことで薬代が安くなります。
病院で処方箋を出してもらい、院外で処方してもらう場合「処方箋料」として680円がかかります。
他にも調剤料、調剤基本料、薬剤服用歴管理指導料などがかかるので、窓口での支払いが割高になることが多いです。
これを「院内処方」にしてもらうと、「処方箋料」が「処方料」になり、420円になります。
調剤料や他の項目の負担も抑えられるので、窓口での負担が軽減されるのです。
調剤薬局の利用を避けたい場合は、「院内処方」に対応している医療機関を使うことも検討してください。
薬代が払えないときに使える5つの制度
毎月の薬代が高すぎる場合は、医療費を軽減するための公的な制度を利用できないかどうか調べてみましょう。
国保でも社保でも、何らかの健康保険に入っている方なら対象になる可能性が高いです。
また、事情があって現在保険証を持っていない人が利用できる制度もあります。
事前に申請してお金を振り込んでもらうものや、支払った金額を後から補てんしてもらえるものなどがありますので、まずは自分が利用できる制度について知っておきましょう
高額療養費制度の申請
ひと月の医療費が一定額を超えた場合、超えた分が払い戻される制度です。
通常は申請してから払い戻しまで3ヶ月以上かかりますが、加入している保険組合にあらかじめ申請して「限度額適用認定証」などをもらっておけば、窓口負担も軽減されます。
対象になる医療費は「保険適用される診療に対し、患者が支払った自己負担額」ですので、保険適用の薬代はもちろん対象です。
月の医療費の上限額は所得や年齢によって変わりますが、平均的な月収の現役世代であれば月8万円ほどになります。
特に手術や入院などで医療費が高額になった場合は対象になる可能性が高いので、忘れず申請しましょう。
高額医療費貸付制度の利用
高額医療費貸付制度は、上でご紹介した「高額療養費制度」で、いったん窓口での全額支払いが必要になった場合、高額療養費が支給されるまでの間、無利子で費用を借りられる制度です。
借りられる額は「高額療養費支給見込額の8割相当額」となっています。
申請するためには、加入している健康保険組合に「高額医療費貸付金貸付申込書」および医療費の請求書などの各書類の提出が必要です。
返済は簡単で、高額療養費の給付金がそのまま返済金として充てられます。
参考: 原発性マクログロブリン血症・リンパ形質細胞性リンパ腫ナビ【高額療養費制度について 】
無料低額診療制度の利用
無料低額診療は、経済的に困窮している低所得者やホームレス状態にある人、DV被害者などが無料または低料金で医療を受けられる制度です。
実施している医療機関が決まっており、全国に約700カ所あります。
診療内容や減免額などは病院によって異なるため、確認が必要です。
また、薬代が減免の対象になる自治体は現在のところ限られていますので、その点も合わせてご確認ください。
希望する場合は、住んでいる自治体の社会福祉協議会や福祉事務所に相談しましょう。
傷病手当の申請
傷病手当金は、仕事以外の病気やケガで就業できず給与が受け取れない場合に申請できるお金です。
以下の条件をすべて満たす場合に申請できます。
- 業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
- 仕事に就くことができないこと
- 連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
- 休業した期間について給与の支払いがないこと
傷病手当金の受給額は、1日あたり「直近12ヶ月の標準報酬月額を平均した額÷30日×3分の2」です。
つまり、普段の給与の3分の2を受け取ることができます。
傷病手当金が支給される期間は「支給を開始した日から通算して1年6ヵ月」です(令和4年1月1日より)。
該当する方は雇用主または会社の事務などに相談してください。
医療費控除を利用する
医療費控除も有効な手段ですが、これはその場で利用できる方法ではありません。
1月1日から12月31日の治療費が10万円を超えた場合、その超過額を所得から差し引けるものです。
利用には確定申告が必要であり、生計をひとつにする家族の分であれば合算することができます。
医療費控除の対象となるのは、次のような医療費の項目です。
- 入院費
- 治療費
- 鍼灸、マッサージ
- 通院費用、交通費
- 出産の入院費用
- 虫歯、金歯、入れ歯などの治療費
- 医薬品
特に「治療」が発生するものが当てはまることがわかります。
もちろん薬局で処方箋や医薬品を購入し、1年間で10万円を超えれば医療費控除が利用できます。
一方で「美容整形費用」「自己都合での歯列矯正」などは含まれません。
平成29年からは医療費控除において、領収書・レシートの提出が必要なくなりました。
ただし全く必要なくなった、というわけではありません。
明細書はしっかりと保管した上で、5年分はいつでも提出できるよう整理しておきましょう。
セルフメディケーション税制とは?

2017年から2021年12月31日までの間、医療費控除の特例として「セルフメディケーション税制」が実施されています。
市販で販売されている「OTC医薬品」を購入し、1年間で12,000円以上になった場合、その超過額が所得控除の対象になります。
厚生労働省で指定された83の成分を含む、1600品目が対象となっています。
「ロキソニンS」「イブ」「エスタックイブ」「サロンパス」など、有名な商品も対象です。
OTC医薬品であるかどうかは、以下のマークがパッケージにあるかどうかで見分けられます。
ただし対象商品であってもマークがない場合があるので、心配な時は薬剤師に確認してみましょう。
平成30年1月現在の対象品目:https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000197976.pdf
薬代を払わないと「調剤拒否」の可能性も

保険治療の効く薬であれば、窓口での負担はいくらか軽減することができます。
しかし「後日支払います」と言ってその後来店せず、そのまま未払いになってしまう人もいます。
薬剤師には「応召義務(薬剤師法第21条)」という義務があるため、原則としては調剤に応じる必要があります。
この義務には罰則さえないものの、場合によっては業務停止、免許の取り消しなどの処分を受ける場合があります。
しかしだからといって、「調剤を断れないなら代金を支払わなくてもいい」というわけではありません。
薬局から取り立てが来ることはある?

薬代を未払いのまま放置すると、薬局が弁護士に依頼し、債権回収を行う可能性があります。
- 薬剤師が調剤した薬を受け取っていること
- その薬の代金が支払われていないこと
上記2点が立証される場合、催促や督促が行われるリスクがあります。
未払い額が膨らみ、悪質だと見なされれば内容証明郵便が送付されて裁判の準備が進められます。
そして最終的に訴訟にまで発展してしまうと、未払いであることを立証され、強制執行が行われてしまうのです。
強制執行が行われると、給与や預金口座、自動車や住宅などの財産が差し押さえられることになってしまいます。
大きな病気を抱えて薬代も払えないでいるのに、さらに財産を奪われてしまう……
そんな状況だけは避けなければいけません。
そうなる前に、できるだけ早く主治医に薬代を抑えることができないかどうか相談してください。
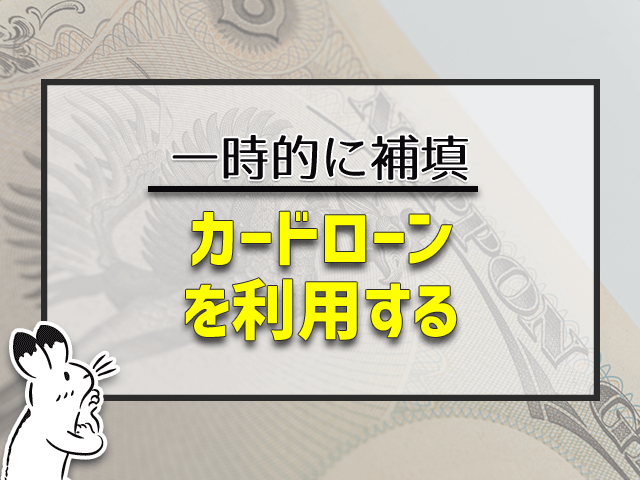
薬代を調達する方法がなくて困り果てている場合は、カードローンの利用も視野に入れましょう。
お金がないからといって病院に行くことを渋る人もいますが、もし重症だった場合は大変なことになってしまいます。
そのあとの治療費のことも考えると、多少利子がかかってでもカードローンを利用した方が良いと言えるでしょう。
高額な借入の場合は生活を圧迫することになってしまいますが、それでも健康は何者にも代え難いものです。
どうしても現金化が足りない時は「クレジットカード現金化」!
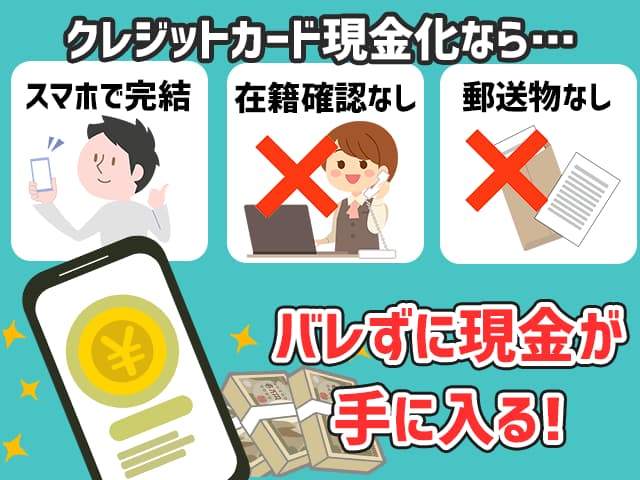
- スマホで完結!
- 会社や自宅への確認の電話なし!
- 郵送物がなく周囲にバレない!
一時的とはいえ、薬代にカードローンは抵抗が……という方も、もちろんいますよね。
そんな時におすすめなのが「クレジットカード現金化」です。
クレジットカードでショッピングをするだけなので、手続きはスマホで全て完結!家族や周囲にバレることもありません。
もちろんお見積りは無料!クレジットカードでいくら現金が貰えるのか、まずはチェックしてみて下さいね!
まとめ:薬代が払えないときは病院に相談!
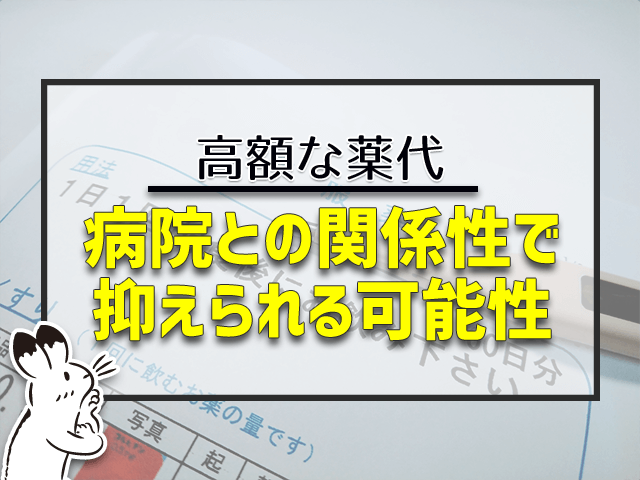
今回は薬代が払えないときの対処法について解説してきました。
薬代が高額になると、通院するのもためらってしまいますよね。
できるだけ価格を抑えた薬を使いたいけど、なかなかお医者さんに言い出しにくい……という場合もあると思います。
確かにお医者さんは病気に関するプロですが、生活費に関するプロではありません。
患者さんの生活がどれだけ苦しくても、言い出さないことには把握しきることはできないのです。
どうしても薬代が捻出できない場合、まずは主治医と相談して、処方してもらう薬を変えられないか話してみましょう。
健康は何にも代え難いものです。
「薬代を節約する」という考え方は、できるだけ避けるべきでしょう。